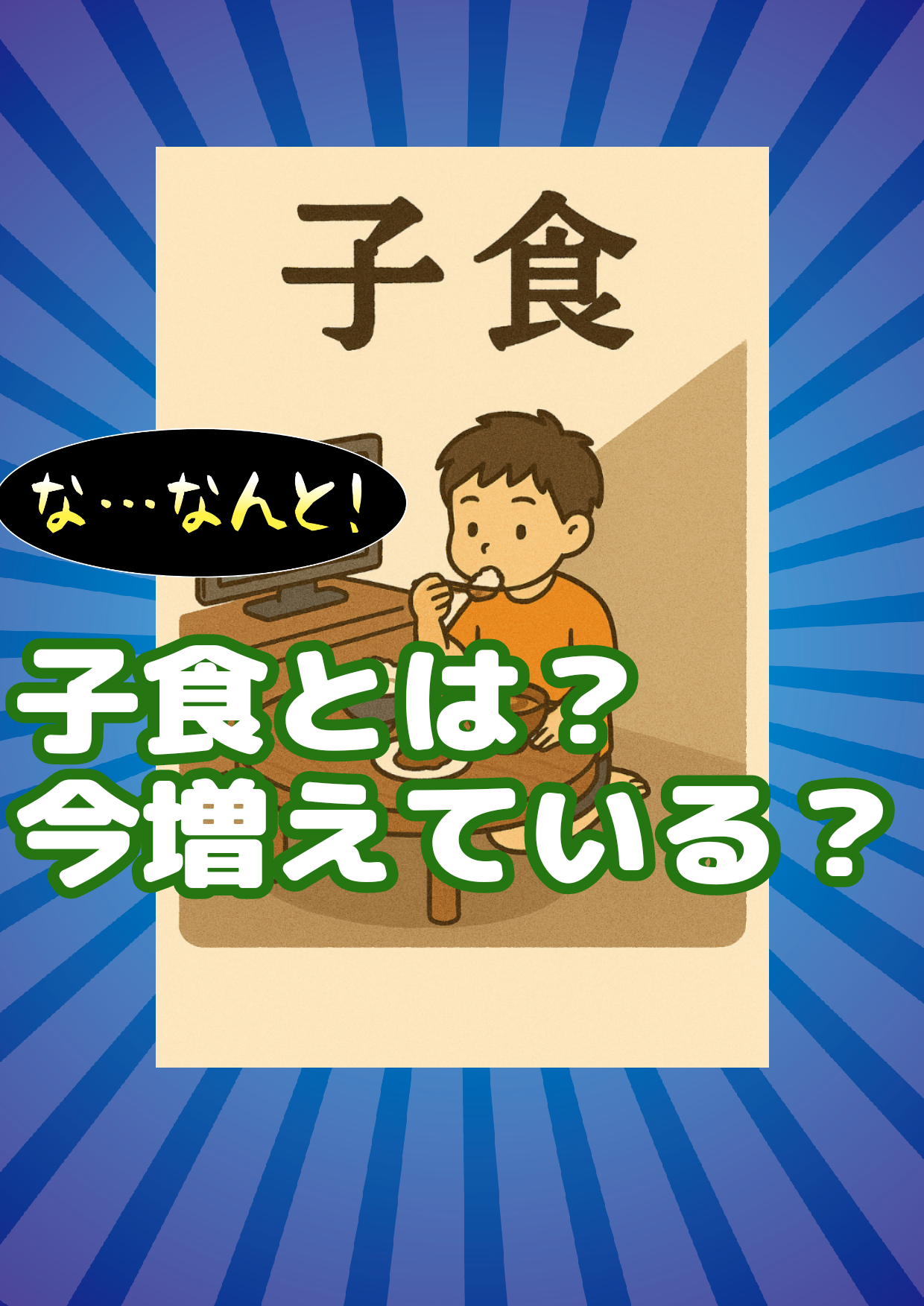
しばこです。
「子食(こしょく)」という言葉を聞いたことがありますか?
子どもが子どもだけで食べる習慣のことを指します。
現代の共働きや塾・習い事のスケジュールから、子食は増加傾向にあります。
一見、仕方のないことのようですが、栄養・会話・食育の面で気をつけたいリスクも。
この記事では、子食の定義・デメリット・防ぐ工夫を分かりやすく解説します。
目次
子食とは?
子食(こしょく)とは、子どもが子どもだけで食事をする習慣のことです。
共働き家庭の増加、習い事や塾で帰宅時間がバラバラになるなど、生活リズムのずれから子食は起こりやすくなっています。
「子どもだけでも食べてくれるなら安心」と思うかもしれませんが、長く続くと食育や心の発達に影響が出る場合もあるのです。
子食のデメリット
子食が続くことで起こりやすい問題を整理しました。
- 栄養の偏り:簡単に食べられる菓子パン・おにぎり・カップ麺などに偏りがち。タンパク質・野菜が不足しやすい。
- 会話不足・食育機会の減少:家族の会話から自然に学べる「食べ方・マナー・文化」が育ちにくい。
- 食事の楽しみが減る:誰かと一緒に「美味しいね」と共有する体験が少なく、食への関心が下がる。
- 孤独感:家庭内にいても孤独を感じやすく、心理的な影響につながることも。
子食を防ぐ工夫
毎日家族全員がそろうのは難しいですが、ちょっとした工夫で子食を減らすことはできます。
1. 5分でも一緒に食卓を囲む
短時間でも「同じ時間に一緒に座って食べる」ことで、子どもは安心感を得られます。
2. 同じ料理を一口でも共有する
親子で全く同じ献立を食べるのが理想ですが、難しいときは1品だけでも共通にするのがおすすめ。味噌汁や果物など取り入れやすいものから。
3. 週末だけは家族で共食
平日は難しくても、休日の朝食や夕食だけは家族そろって食べるとリズムが整います。
孤食気味の家族(仕事で遅い夫など)のリカバリーにも。
まとめ
子食(こしょく)は、忙しい家庭では誰にでも起こり得る習慣です。
ただし、続くことで栄養不足・会話やマナー不足・孤独感などのリスクがあります。
完璧を目指す必要はなく、「ちょっと一緒に」「同じものを少しでも」を意識するだけで効果があります。
日々の中で「共食の瞬間」を増やす工夫を取り入れてみましょう。
関連記事
・個食|一人一人違う食事になるときの工夫
・孤食|一人ご飯でも心を満たす工夫
・固食|偏った食習慣をゆるやかに整える工夫
・(次回予告)5つのこ食まとめ記事+チェックリスト
※本記事は食育・整活の視点でまとめています。ご家庭の状況に応じてアレンジしてご活用ください。

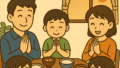
コメント